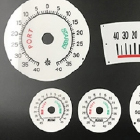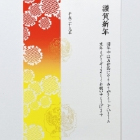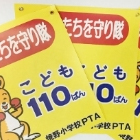シルクスクリーン印刷における素材別注意点
シルクスクリーン印刷では、素材よって印刷すべき注意点が異なります。
素材が持つ特性や条件に合わせて、インクや印刷方法や治具(印刷するために制作する器具)の必要性を検討する等、経験と実績が仕上がりを大きく左右します。又、調色にあっては、匠の技とも言えるべき方法で指定色を制作します。
以下には、素材毎に関する注意点を掲載しておりますので、シルクスクリーン印刷をご検討される際にご確認ください。
金属素材
- 印刷可能条件: フラットな表面であることが必須です。
- 塗装済み金属の場合:
塗装の種類(粉体塗装、ウレタン塗装等)の事前確認を行います。
既存塗装の焼き付け温度を確認し、把握します。
既存塗装を侵さないように、既存塗装焼付温度より低い温度でシルク印刷の焼き付け実施するためです。
例:150°で焼付塗装されていれば、150°以下でシルク印刷の焼き付けが必要 - 例えば、未塗装金属の場合:
ステンレスなら100度で60分の焼き付けを実施します。 - 表面がザラつく鉄(黒丸など)は、シルク印刷には向きません。
- 金属ケース(成形物)などは、フチの盛り上がりやビス部分などに凸凹がある場合シルク印刷できません。(基本的に、組立後の成形物印刷は難しい)
- 印刷する金属に、「キズ」が入っている場合には、印刷後も残るので確認が必要です。
- 色指定:
シルク印刷は、白・黒以外は全て調色となりますので、日本塗料工業会の色見本やPANTONE、DIC等の色見本チップが必要です。(印刷物の切れ端など、色のわかるものならOK)

木材素材
- 表面加工処理が、重要になります。
- 軽いクリア塗装済みであれば問題ありません。
- 生木の場合は、樹脂の浮き上がりに注意が必要になります。
又、割れたり反ったり、キズがあったりしますので、支給材は入念に確認します。
印刷面を削っていただくことになります。 - 構造上の制約として、「節」がある部分は印刷できません。(色がのりません)
- 30mm以下の薄い材料は反りやすく要注意です。
- 1枚板は湿度・温度によって膨張率が変化するため、変形リスクがあります。
- 使用インクは、 表面処理次第で適切なインクを使用します。
- 木材の場合の角部分は、糸面として削ってあるためギリギリまでは印刷できません。
- デザインとしては、 木目を活かしたデザインが一般的で、ベタ塗りは稀です。
- 合板の場合、ベニヤでも種類(シナベニヤ・ラワンベニヤ等)があるため、印刷面の状態について、必ず確認させていただきます。
- 支給材の場合でも、サンプル作成してご確認いただきます。

樹脂素材(アクリル・塩ビ・PET等)
- アクリル板の種類としては、キャスト版(表面が平滑で印刷に適しているが、価格は2割高)と、押出版(表面に微細な凹凸があり印刷品質に影響)があります。
推奨は、キャスト版になります。(お客様は、ご存じない方がほとんどです) - 大きなサイズで、ベタ塗りなどをご要望の場合には、静電気対策が必要になります。
特に塩ビは、静電気でホコリを引き寄せやすい性質があります。
クリーンルームなど設備をお持ちの印刷会社での対応となる場合や静電気対策のグローブ等を使用されての対応となります。
ちなみに、ターポリンは、溶剤系インクジェット印刷が主流であり、弊社でも対応します。 - 素材の特徴として、アクリルは透明度が高い、FRPは割れに強い、ペット(PET)は、アクリルよりも透明度が高いとなります。
- アクリルの場合は、厚さで金額や工程が異なり、通常は3mmです。一般的ではない厚み(2mm、5mmなど)は、別工程が入ることから金額的には高くなります。
又、加工の違いとして、アクリルは、レーザーカットが可能ですが、塩ビは可燃性の素材のため、レーザー加工は出来ません。
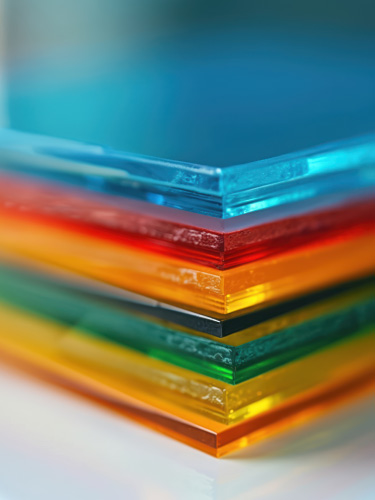
皮革素材
- 天然皮革の特徴として、部位により厚みが不均一です。
コンマ数ミリの差でも印刷に影響します。
1枚ものの皮では、使用不可部分が存在します。(傷、刻印等) - 細かい文字やマークの印刷には不向きです。
- 合成皮革は、 厚みが均一ですのでシルク印刷には適しています。

石材
- 自然石でも印刷は出来ますが、表面を平滑に削った状態が必須です。
又、印刷するための治具(印刷時に固定するための道具)が必要な場合があり、価格的には高くなります。 - 自然石を手作業加工によって削られている場合がありますが、厚みのばらつき(0.5mm程度)が印刷品質に影響しますので、必ず確認させていただきます。
- 印刷時には、縁や角に異物や粉塵が付着している場合が多いことから、除去作業が必要になる場合がほとんどです。

ガラス素材
- 二液硬化型インクを使用します。(表面に固着させる方式)
- 焼き付け硬化または自然乾燥による硬化が必要であり、時間を要します。
乾燥用の治具が必要な場合もあります。 - 現場施工時は防塵対策と乾燥時間の確保が重要になります。